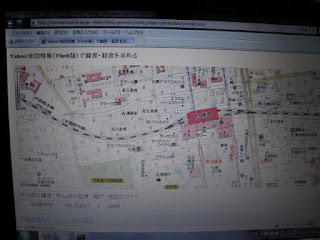今年の狩猟解禁も昨年と同じく10月1日の予定。解禁までの時間の使い方でその年の猟果も決まってくるのかなと思いながら毎日を過ごしている。
そんな中でGarminのハンディGPS「etrex20」も山での出番がほとんどないのだが、ネットで色々と調べていると、本体以外に付属して多くの活用方法があるらしい。
サイトでよく見かける「Yahoo地図」であるが、これを切り出して「etrex20」の本体に入れ、持ち運びができるようなのだ。
さらに「電子国土」の地図も切り出して持ち運びできるとのこと。等高線地形図を使えることで山の中での行動範囲もさらに広げることができそうだ。
「【ymapjnx】Garmin BirdsEye JNX 作製ツール」のページより 「ymapjnx」と「gsijnx」をダウンロードする。ちなみに 「ymapjnx」は「Yahoo地図」、「gsijnx」は「電子国土」を切り出して、GarminのGPSに入れることができるフリーソフトである。
「ymapjnx」も「gsijnx」もそれだけでは使うことができない。「Python2.7.3」というフリーソフトが必要で、このフォルダに解凍した 「ymapjnx」と「gsijnx」のフォルダを入れる。また、地図を表示するためには日本語パッチを「etrex20」にインストールしなければならず、なかなか手間がかかる作業である。
「ymapjnx」のフォルダ内にある「config」を切り出す地図の範囲を指定して書き換え、「start」のバッチファイルをクリックすると切り出した地図の作成が始まる。大きな範囲を指定するとかなりの時間がかかるので、北海道を4分割にして作成した。
終了するとフォルダ内にjnxファイルが出来上がっているので、これを「etrex20」の本体にコピーするが、本体メモリだけでは足りないので32GBのmicroSDを購入してコピーした。
「Yahoo地図」はこんな感じで表示される。道路や文字もはっきり読み取ることができる。カスタムマップと違ってスクロールもスムーズなので実用性には全く問題ない。
同様の方法で「gsijnx」を使って「電子国土」を切り出した地図を作成してみた。等高線もくっきり映っており、湖や川、登山道も忠実に再現されている。これなら山でも十分使える。
今回 「ymapjnx」と「gsijnx」のおかげで「etrex20」のレベルが一気にあがったと思う。こんな素晴らしいソフトを開発した作者に感謝したい。